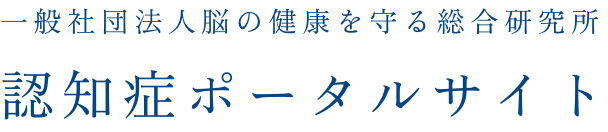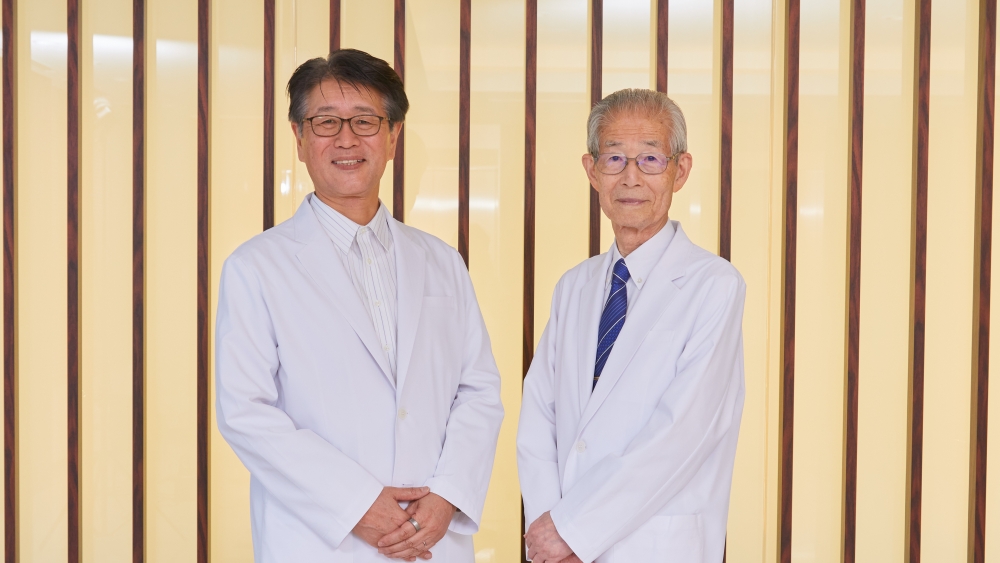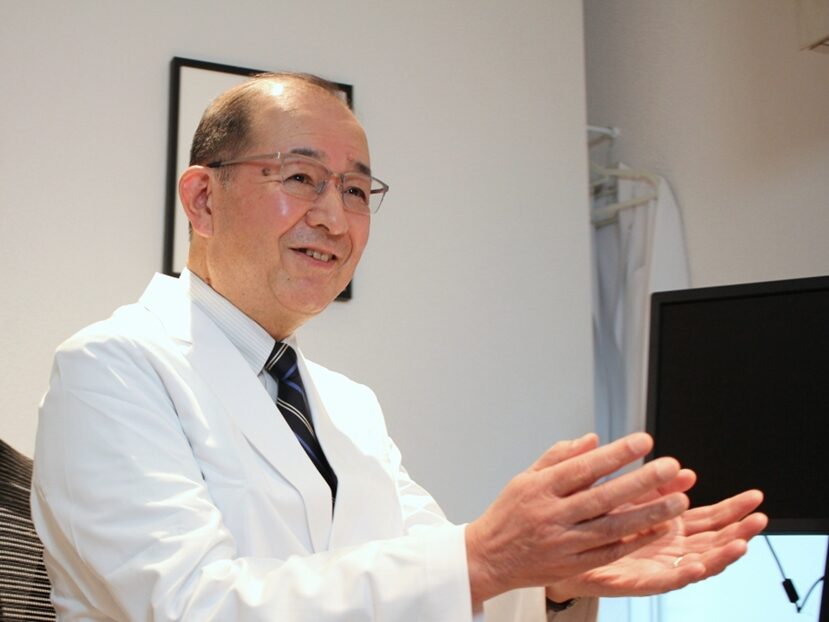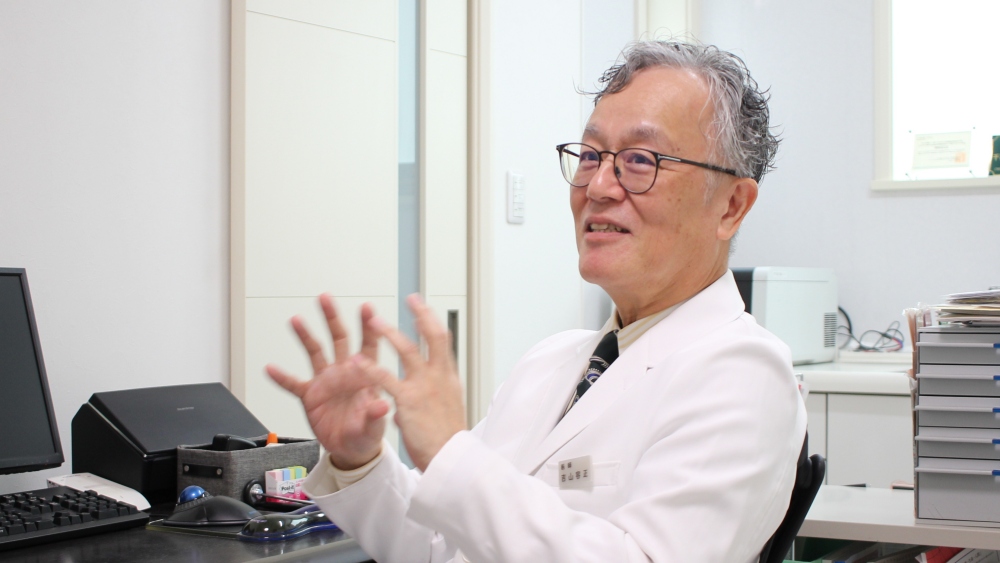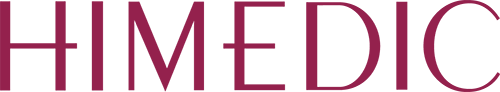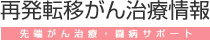認知症リスクを高める14の要因とは? ならないための予防策も解説

認知症は加齢だけが原因ではなく、生活習慣や環境、健康状態も大きく関わっています。国際的な医学誌「The Lancet(ランセット)」は、14の修正可能なリスク因子を改善することで、認知症の約40%を予防または発症を遅らせる可能性があると報告しています。
認知症の発症リスクを高めることが科学的に示されている14の要因と、日常生活でできる具体的な予防策について、エビデンスをもとに解説します。
認知症の原因となる14のリスク因子とは
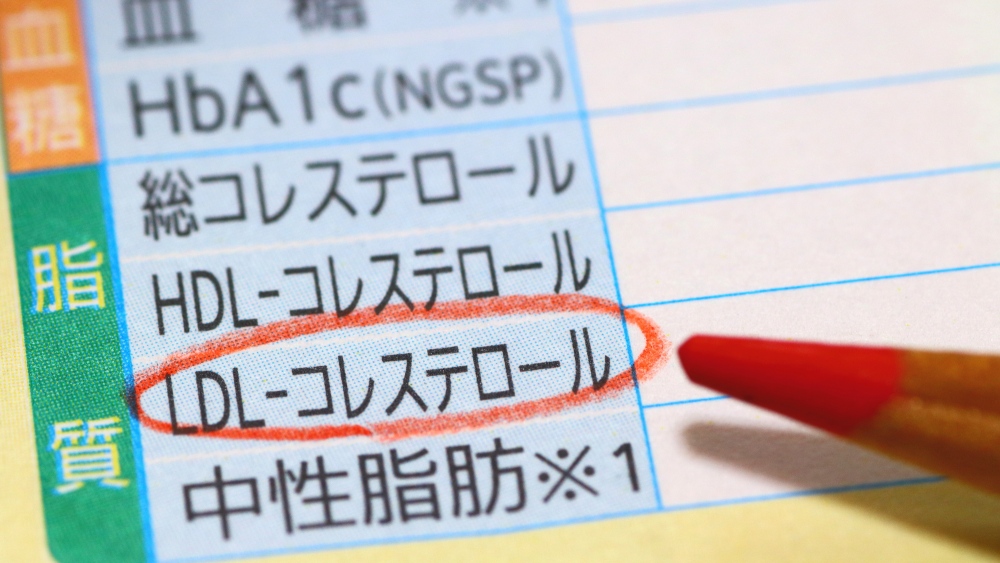
国際的な医学誌「The Lancet(ランセット)」では、認知症のリスクを高める14の因子を明らかにしています。これらの因子は、私たちの生活習慣や環境要因と密接に関わっており、意識的な取り組みによって改善が可能です。
認知症のリスクを高める14の因子とは、以下のとおりです。
- 教育の不足
- 難聴
- 高LDLコレステロール
- 外傷性脳損傷
- 高血圧
- アルコールの過剰摂取
- 肥満
- 喫煙
- うつ
- 社会的孤立
- 身体活動不足
- 糖尿病
- 大気汚染
- 視力障害
1. 教育の不足
教育は脳の神経ネットワークを発達させて、「認知予備能」を高める効果があります。認知予備能とは、脳にダメージがあっても正常な機能を維持できる脳の余力のことです。
幼少期から青年期の教育が特に重要で、複雑な思考や問題解決能力を身につけることで、脳の神経回路が発達しますが、成人になってからでも、読書や学習活動を続けることで脳を刺激し続けられます。
2. 難聴
聴力の低下は、脳への音情報が減ることで脳活動が低下し、認知機能に悪影響を与えます。聞こえにくくなると、会話についていくために脳により多くのエネルギーを使うようになり、記憶や思考に使える脳の力が減ってしまいます。
また、難聴により人とのコミュニケーションが困難になり、社会的な孤立を招きやすくなることも認知症リスクを高める要因となります。中年期(45〜65歳)の聴覚障害がある人は、正常な聴力の人と比べて認知症になるリスクが約2倍高いことが分かっています。
3. 高LDLコレステロール
中年期における高LDLコレステロール(悪玉コレステロール)は、動脈硬化を促進し、脳血流の低下やアミロイドβの蓄積を引き起こすことで、認知症リスクを高めると報告されています。
食生活の改善や運動習慣、必要に応じたスタチン(LDLを下げる薬の総称)の使用によりLDL値を適正に保つことで、将来の認知症予防につながります。
4. 外傷性脳損傷
脳に直接的なダメージを受けると、認知症の原因となる異常なタンパク質の蓄積が促進されます。スポーツや交通事故、転倒などによる頭部外傷は、軽度であっても脳に影響を与える可能性があります。
特に問題となるのは、繰り返し頭部に衝撃を受けることです。軽度な衝撃でも繰り返し受けることでリスクはさらに高まり、5回以上の外傷では認知症リスクが約3倍まで上昇することが報告されています。
5. 高血圧
血圧が高い状態が続くと脳の血管に負担がかかり、動脈硬化などによって血流が悪化します。脳は酸素と栄養を豊富に必要とする臓器のため、血流の悪化は神経細胞の機能低下を招きます。
また、高血圧は小さな脳梗塞を引き起こしやすく、これが積み重なることで認知機能が徐々に低下していきます。中年期の高血圧は特に影響が大きく、50歳で血圧が高い人は将来の認知症リスクが高くなることが研究で明らかになっています。
アルコールの過剰摂取
大量の飲酒は、脳の神経細胞を直接的に傷害し、特に記憶を司る海馬という部位の萎縮を引き起こします。アルコールは脳に対して毒性があり、長期間の過剰摂取により脳の容積が減少することが知られています。
アルコール依存症の人の認知症リスクは、男女ともに約3倍高くなることが知られています。特に65歳未満で発症する若年性認知症の半数以上にアルコール問題が関わっていることも報告されています。
肥満
肥満は糖尿病や高血圧などの生活習慣病を引き起こし、これらが脳血管に悪影響を与えます。また、肥満そのものが体内で慢性的な炎症状態を作り出し、この炎症が脳の神経細胞にダメージを与える可能性があります。
中年期にBMI30以上の肥満状態にある人は、適正体重の人と比べて将来の認知症リスクが約1.3倍高くなることが大規模な研究で確認されています。
喫煙
タバコに含まれる有害物質は血管を収縮させ、脳への血流を悪化させます。また、喫煙により体内で活性酸素が増加し、これが脳の神経細胞を攻撃してダメージを与えます。長期間の喫煙は脳の血管病変を引き起こしやすく、血管性認知症のリスクを高めるのです。
喫煙者の認知症リスクは非喫煙者と比べて明らかに高く、受動喫煙でも記憶力の低下が見られることが報告されています。
うつ
うつ状態が続くと、脳の重要な部位である海馬や前頭葉に萎縮が起こることが知られています。これらの部位は記憶や判断力に重要な役割を果たしているため、萎縮により認知機能が低下します。
また、うつ病は認知症の前段階の症状として現れることもあり、認知症の初期段階で気分の落ち込みが生じる場合があります。大規模研究では、うつ病の経験がある人は認知症リスクが約2倍高いことが明らかになっています。
社会的孤立
人との交流が少ないと、脳への刺激が減少し、言語機能や記憶力を使う機会が減ってしまいます。脳は「使わないと衰える」特性があるため、社会的な交流の不足は認知機能の低下につながります。
独身の人や配偶者を亡くした人は、既婚者と比べて認知症リスクが高いことが世界各国の研究で一貫して報告されています。質の高い人間関係を持つ人ほど、認知症になりにくいことも分かっています。
身体活動不足
運動不足は脳への血流を低下させ、神経細胞の新生(新しい細胞が生まれること)を妨げます。運動は脳の健康維持に重要な物質の分泌を促進するため、運動不足はこれらの恩恵を受けられなくなることを意味します。
長期間の運動不足がある人は、活発に身体を動かす人と比べて認知症リスクが約1.4倍高いことが報告されています。特に中年期からの継続的な運動不足は、将来の認知症リスクに大きく影響することが分かっています。
糖尿病
高血糖状態が続くと、脳の血管に障害が生じ、血流が悪化します。また、インスリンの働きが悪くなることで、脳内でアルツハイマー病の原因となる異常なタンパク質が蓄積しやすくなるとされています。
糖尿病患者の認知症リスクは、健康な人と比べて約1.6倍高く、糖尿病の罹病期間が長いほど、また血糖コントロールが悪いほどリスクが上昇することが知られています。
大気汚染
PM2.5などの微細な汚染物質は、呼吸を通じて体内に入り、血流に乗って脳に到達します。これらの物質は脳で炎症や酸化ストレスを引き起こし、神経細胞にダメージを与えます。
大気汚染の濃度が高い地域に住む人は、きれいな空気の地域に住む人と比べて認知症になりやすいことが複数の研究で報告されています。特に交通量の多い道路沿いに住む人では、認知症リスクの上昇が顕著に見られます。
視力障害
視力の低下や未治療の目の病気は、近年、認知症の新たな危険因子として注目されています。視力が落ちると脳への刺激が減り、社会的な交流も減少しやすくなるため、認知機能に悪影響を及ぼすと考えられています。
白内障や糖尿病網膜症などの疾患を適切に治療すると、認知症リスクが下がる可能性が報告されています。定期的な眼科検診と早期治療は、視力を守るだけでなく、認知症予防にもつながる重要な対策です。
認知症にならないためにできること

Lancetによると、リスク因子を改善することで、認知症の約40%を予防または発症を遅らせる可能性があるとされています。認知症の原因となる物質の脳への蓄積は、若い頃から始まっており、早期から予防に取り組むほど効果が高く、また、中年期以降に始めても十分な効果が期待できます。特に重要な予防策は以下のとおりです。
血圧を管理する/運動習慣を持つ
血圧管理は認知症予防の重要な柱の一つです。適切な管理により認知症リスクを大幅に軽減できます。
血圧管理の基本は生活習慣の見直しと薬物療法の組み合わせです。生活習慣では、塩分の摂取を控えめにして、定期的な運動を実践することが重要です。
運動療法では、ウォーキングやスロージョギングなどの有酸素運動が推奨されます。習慣的な有酸素運動には血圧を低下させる効果が期待でき、認知症リスクの軽減につながります。
【関連記事】エビデンスが裏付ける、本当に有効な認知症予防策とは?
タバコをやめる
喫煙は百害あって一利なしの代表例で、認知症リスクを確実に高める因子です。ニコチンは血管を収縮させ、一酸化炭素は酸素運搬能力を低下させます。これらの作用により、脳への酸素供給が慢性的に不足し、脳へ悪影響をもたらします。
効果的な禁煙方法として禁煙外来の利用が有効で、禁煙外来を利用すると約7割の方が成功しているという報告もあります。禁煙は、認知症予防以外にも心疾患や脳卒中の予防にもつながるため、何歳から始めても遅すぎることはありません。
難聴を放置しない
難聴は認知症のリスク因子の一つでありながら、軽視されがちな問題です。聴力の低下は段階的に進行するため、定期的な検査による早期発見が重要です。
難聴への具体的な対処法は、以下のとおりです。
- 定期的な聴力検査による早期発見(特に50歳以降は年1回)
- 適切な補聴器の使用
- 耳垢除去などの基本的なケア
- 騒音環境や大音量での音楽鑑賞を避ける
社会とのつながりを保つ
人との交流は脳を刺激し、認知機能を活性化させる重要な要素です。社会的孤立は、認知症の発症にとどまらず、心身の健康にも大きく関わります。家族や友人との定期的な交流や、仕事を引退した後でも趣味のサークルやクラブ活動、地域のボランティア活動への参加するなど、社会とのつながりを持つようにしましょう。
改善行動で認知症の発症リスクは下げられる
認知症は、私たちの日常生活や環境と深く関わる病気です。高血圧、喫煙、運動不足などのリスク因子は、意識的な行動で改善が可能です。
今回示した14のリスク因子を避けることで、将来の発症リスクを大きく減らせる可能性がありますし、仮に認知症状が出始めた後でも、改善行動を取ることで進行を遅らせたり、正常な状態に戻ることができる可能性もあります。今できることから始めてはいかがでしょうか。
■参考文献
取材・監修にご協力いただいた先生
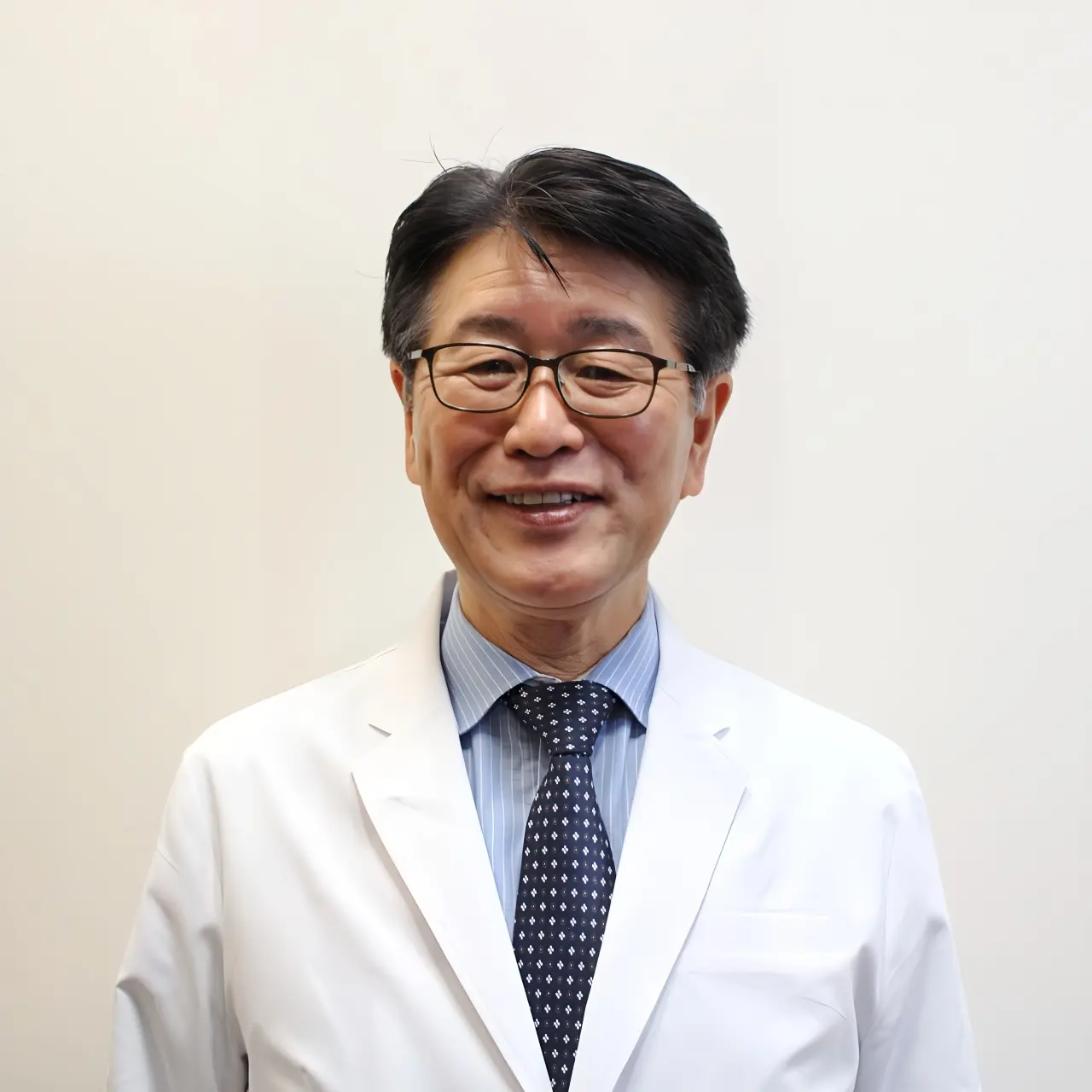
一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事
東京ミッドタウンクリニック 総院長
田口淳一(たぐち じゅんいち)医師
1984 年 東京大学医学部卒業1993年ワシントン大学へ留学
東京大学医学部附属病院助手、元宮内庁侍従職侍医、東海大学医学部付属八王子病院循環器 内科准教授を経て、2007年 東京ミッドタウンクリニック院長、2010年 東京ミッドタウン先端医療研究所所長、2020年5月 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック総院長、2024年5月 東京ミッドタウンクリニック総院長。2024年9月 一般社団法人脳の健康を守る総合研究所 代表理事に就任。
※掲載している情報は、記事公開時点のものです。